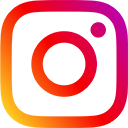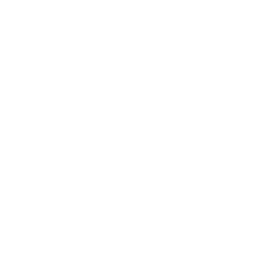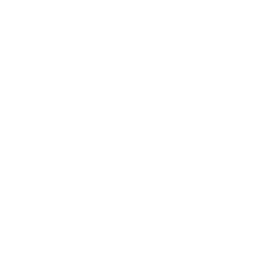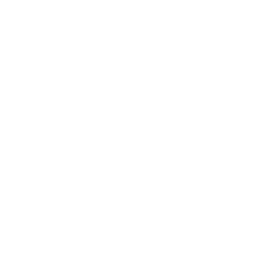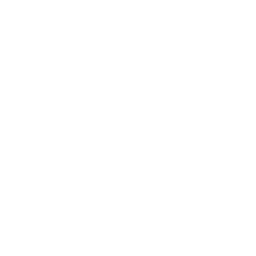秋の心温まる日々:お彼岸の意味と習慣
暑い日々が続きますね。暑さ寒さも彼岸までということわざがありますが、早く涼しくなってほしいです。ということで今回はお彼岸について書きたいと思います。
秋季お彼岸
秋分の日は「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」日として制定されました。また昼夜の長さがほぼ等しい日で、季節の変わり目を示す日として重要視されています。お彼岸は、この日を起点に前後3日間の期間内に行われ、合計で7日間にわたります。
お彼岸の意味と由来
「日本後記」に806年に日本で初めて仏教行事として彼岸会が行われたとあります。そこから現在に至るまで続いているのがお彼岸です。
お彼岸には、故人を供養し、感謝の気持ちを表すための意味が込められています。この期間中、仏壇にお線香やお供え物を捧げ、先祖の霊を慰め、自身の心を清めることが一般的です。また、お墓参りも行われ、墓地を清掃し、お墓に花を手向けることが一般的です。
お彼岸は、仏教の教えに基づくもので、生死の繰り返しという輪廻転生の考え方に基づいています。この時期に先祖の霊を供養することで、彼らの魂が安らかに成仏することを願うとともに、自身も清浄な心を保つことが大切だとされています。
お彼岸の習慣と行事
秋季お彼岸には、以下のような習慣や行事が行われます。
- お供え物の準備: 仏壇には、白いご飯や野菜、果物、お線香、花、牡丹餅などが供えられます。これらの供物は、故人に捧げるものとして用意され、感謝の気持ちが込められています。
- お墓参り: 秋季お彼岸には、墓地への訪問が行われます。お墓を掃除し、新しいお花を植えたり、お墓に手を合わせたりします。これも、ご先祖様に感謝を伝えるための大切な行為です。
- 法要や読経: 仏教寺院では法要が行われます。これに参加することで、安寧と清浄な心を求めることができます。
まとめ
秋季お彼岸は、日本の伝統的な仏教行事で、故人を供養し感謝の気持ちを表す大切な期間です。お供え物の準備やお墓参り、法要など、多くの習慣と行事が行われ、安寧と清浄な心を求めるものとして、長い歴史の中、人々に受け継がれています。この時期は家族が集まり、故人を思い出す大切な機会にしたいですね。